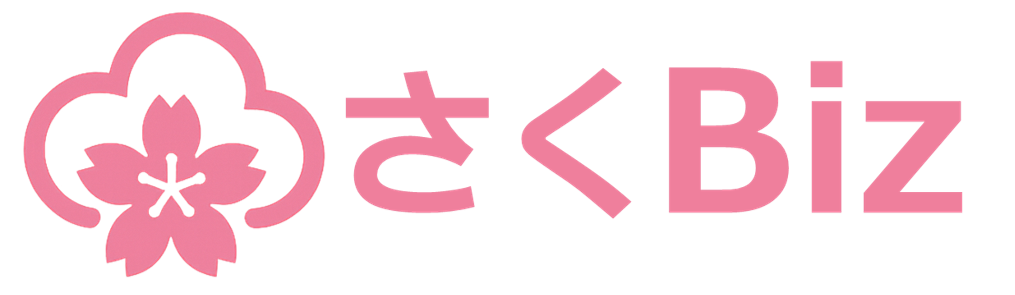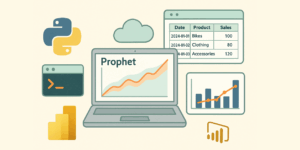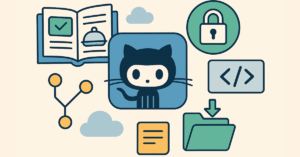OSSとは?中小企業が知っておきたいオープンソース活用の基礎
近年、多くの企業がIT投資の効率化を迫られています。その中で注目を集めているのが「OSS(オープンソースソフトウェア)」です。
たとえば、世界で広く使われている「Linux」や「MySQL」「WordPress」などはすべてOSSです。クラウドやAIの分野でもOSSが欠かせない存在となっており、実際にGoogleやAmazonなど大企業もOSSを基盤として自社サービスを構築しています。
中小企業にとってもOSSは「コスト削減」と「柔軟なIT活用」を同時に実現できる可能性があります。ただし「OSSって無料ソフトのこと?」「ライセンス違反にならない?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では、OSSの基本からライセンス、商用ソフトとの違いまでをやさしく解説し、中小企業が安心してOSSを検討できるように整理していきます。
OSSの基本を理解する
ソフトウェアとは?
「ソフトウェア」とは、コンピュータやスマートフォンを動かすためのプログラムのことです。わかりやすい例としてスマートフォンを考えてみましょう。
OS(基本ソフト):
iPhoneには「iOS」、Androidスマホには「Android OS」が入っています。これはスマホ全体を動かすための土台です。
アプリ(応用ソフト):
LINEやInstagram、会計アプリなどはOSの上で動く「ソフトウェア」です。利用者はアプリをインストールし、料理を「食べる」ようにソフトをそのまま使います。
パソコンでも同じで、WindowsやmacOSといったOSの上で、ExcelやPhotoshopといったアプリケーションが動いています。
料理に例えると、ソフトウェアは「完成した料理」にあたります。ユーザーはレストランで料理を食べるように、提供されたソフトをそのまま利用します。
ソースとは?
ソフトウェアを作るための設計図が「ソースコード」です。これは人間が書いたプログラムで、これをコンピュータが理解して実行することでソフトウェアが動きます。
プログラミング言語にはいくつか種類があります。
Java:銀行システムやAndroidアプリなど大規模なシステム開発で利用
Python:AIやデータ分析で人気
JavaScript:WebサイトやWebアプリでよく使われる
C言語/C++:機械や組み込み機器などの制御に強い
料理に例えると、ソースコードは「レシピ」です。レシピがあれば誰でも同じ料理を再現でき、さらにアレンジして新しい料理を作ることもできます。
オープンとは?
「オープン」とは「公開されていて誰でも利用できる」という意味です。
料理の例で考えると、シェフの秘伝レシピが閉じられたノートにあるのではなく、
・クックパッドのようなレシピ投稿サイト
・YouTubeで料理インフルエンサーが公開する調理動画
といった形で、誰でも無料で見られる状態にあることが「オープン」です。
つまりOSSとは、レシピ(ソースコード)が公開され、誰でも自由に料理(ソフトウェア)を作ったり改良できる仕組みなのです。
OSSのメリットとデメリット
OSSのメリット
コスト削減
WordPress(ホームページ作成ソフト)やLibreOffice(Office互換ソフト)など、多くのOSSは無料で利用できます。ライセンス料が不要なため、中小企業の負担を大きく減らせます。
カスタマイズの自由度
ソースコードが公開されているため、自社の業務に合わせた改良が可能です。たとえば会計システムに独自の帳票を追加するといったことができます。
最新技術を取り込みやすい
世界中の開発者が改善を続けているため、OSSは進化のスピードが速いのが特徴です。セキュリティ修正も早く、最新の技術を試せます。
ベンダーロックインを避けられる
特定のメーカーに依存せず、自分たちで自由に選べるため、契約条件や価格に縛られにくいのも魅力です。
OSSのデメリット・注意点
運用にはITスキルが必要
導入や設定に専門知識が必要なことも多く、社内に技術者がいない場合は外部サポートを検討すべきです。
公式サポートが必ずしもあるわけではない
たとえばMicrosoft Officeならメーカーがしっかりサポートしますが、LibreOfficeの場合は主にコミュニティでの情報共有が中心です。
ライセンス管理が複雑
複数のOSSを組み合わせるとライセンス条件が衝突する場合があります。適切な確認が欠かせません。

OSSライセンスの種類と考え方
OSSは「自由に使える」だけではなく、それぞれに利用条件を定めたライセンスがあります。これは「レシピを無料で配るけれど、改良したらレシピも公開してね」といったルールに似ています。
代表的なライセンスは以下の通りです。
GPL(GNU General Public License)
Linuxが代表例。改良したソフトを配布する際は、同じGPLライセンスでソースも公開する必要があります。共有の精神を重視したライセンスです。
MITライセンス
Ruby on Railsなどが採用。商用利用も自由で、条件はほとんどなくシンプル。
Apacheライセンス
Apache HTTP ServerやAndroidが採用。特許に関する安心感があり、大規模商用利用に適しています。
ライセンスを守ることは、OSSを安心して活用するために欠かせません。
OSSと商用ソフトの違い
商用ソフト(クローズドソース)の例
・Microsoft Office(Word、Excel)
・Adobe Photoshop
・弥生会計
これらは「完成した料理を有料で提供」する形で、レシピ(ソースコード)は非公開。利用者は安心して使える代わりに、カスタマイズはできません。
OSSの例
・LibreOffice(Office互換ソフト)
・GIMP(Photoshopに近い画像編集ソフト)
・Odoo(ERPシステム)
OSSは「レシピも公開」されているため、無料で入手可能でカスタマイズも自由です。ただし利用や運用にはスキルや工夫が必要です。
中小企業でOSSを活用するポイント
必要な機能を見極める
「無料だから」といって導入せず、業務に本当に必要かどうかを判断することが大切です。
外部サポートを活用する
OSSでも有償でサポートを提供する企業があります。自社に技術者がいない場合は積極的に利用しましょう。
商用ソフトと組み合わせる
会計や給与計算などサポートが重要な分野は商用ソフトを使い、社内の情報共有やWebサイトはOSSを活用するといった使い分けが現実的です。
ライセンスやセキュリティを確認
導入前に必ずライセンス条件を確認し、定期的にアップデートが行われているOSSを選ぶことが重要です。
まとめ
OSSは「公開されたレシピを自由に使える料理」のような存在です。中小企業にとって、コスト削減や柔軟なシステム運用を実現できる大きなチャンスとなります。
ただしライセンスや運用体制の理解が必要です。いきなり基幹システムをOSSに置き換えるのではなく、まずはWebサイトや文書作成ツールなど小規模な領域から試してみるのがおすすめです。
OSSをうまく取り入れることで、中小企業は「低コストで強いIT環境」を手に入れることができるでしょう。
これらのサポートをご希望の方はこちらからご連絡ください!