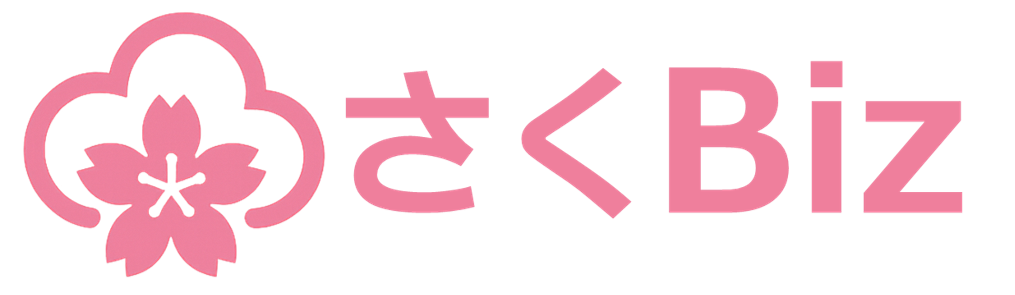Copilotって何?企業の仕事が変わるAIアシスタントの魅力と活用のはじめ方
最近、AIという言葉を耳にしない日はないほど、「AI時代」が身近になってきました。ニュースでは「ChatGPT」や「Google Gemini」の話題が取り上げられ、仕事でも「AIが業務をサポートしてくれる時代が来た」と感じている方も多いのではないでしょうか。
でも、実際に「自分の会社でAIを活用するイメージが湧かない」「個人向けのサービスとは何が違うの?」「本当に業務が変わるの?」――そんな疑問や不安を持つ方も少なくありません。
そこで今回は、Microsoft 365 Copilotとは何か、他の生成AIサービスとどう違うのか、なぜ“企業向け”が大事なのか、やさしく解説していきます。
Copilotとは?カフェの「気が利く店員」にたとえてみよう
まず「Copilot(コパイロット)」の名前の由来ですが、飛行機の副操縦士(コパイロット)の意味。その名の通り、私たちの仕事に“隣で寄り添ってくれる相棒”のような存在です。
たとえば、忙しいカフェで「こんなサービスが欲しいな」と思ったとき、言わなくても気づいて「お水をお持ちしましょうか?」と声をかけてくれる、そんな“気が利く店員さん”がいたらどうでしょう。自分の仕事や時間がグッと効率的になるはずです。
Copilotは、WordやExcel、Outlook、Teamsなど、私たちが日々使っているMicrosoft 365の中に溶け込み、
「議事録をまとめてほしい」
「今までの売上データからグラフを作って」
「メールを短く要約して返信案を作って」
などの“仕事のちょっとした頼みごと”を、自分の代わりにテキパキこなしてくれる存在です。
企業で使うCopilotの強み――「個人向けAI」とはここが違う!
■ 「Copilot」と「ChatGPT」や「Gemini」の大きな違い
最近話題のChatGPTやGemini(GoogleのAI)は、手軽に使える強力なAIサービスです。個人の調べ物やちょっとした文章作成にはとても便利ですが、企業の業務で本格的に活用しようとすると、次のような課題が出てきます。
- 自社のデータ(ドキュメントやメール)を直接扱えない
- セキュリティや情報漏洩リスクへの配慮が必要
- 日本語の業務文書や社内コミュニケーションへの“自然な対応”が課題
Copilotは、まさにこの「企業で本当に使えるか」という観点で設計されたAIアシスタントです。具体的には――
■ 1. 自社データとの連携力が段違い!
Copilotは、Microsoft 365の契約内で管理されているメール、予定表、ファイル、チャット履歴などと直接つながります。
たとえば、
「今週の会議で話したポイントを要約して」
「A社との過去のやりとりをまとめて」
「最新のプロジェクト進捗レポートを作って」
といった“社内業務の文脈”を理解したうえでAIが答えてくれるため、自分だけでなく、チームや会社全体の“仕事の流れ”を踏まえて提案できるのが最大の特徴です。
■ 2. 企業のセキュリティ&ガバナンスが守られる
Microsoft 365 Copilotは、自社のクラウド内(Microsoftの安全な環境)で動くため、「AIに情報が盗まれるのでは?」という不安も最小限です。また、アクセス権限や情報の取り扱いも会社のポリシーに沿ってコントロールでき、外部サービスのような「情報の外部流出リスク」を極力減らしています。
■ 3. “業務で使える”日本語コミュニケーション&ビジネス文書力
企業で求められる日本語のビジネス文書やメール表現にもCopilotは強みがあります。WordやOutlook、Teamsで“使える表現”を自然に提案してくれるため、AIが作ったとは思えない仕上がりに。これがChatGPTやGeminiでは難しい、業務現場で“本当に使える”文章・提案です。
Copilotでできること・できないこと――「得意」「苦手」を知っておこう
Copilotの魅力を一言で言えば、「あなたが普段やっている“繰り返し作業”や“考えるのに時間がかかること”を、隣で一緒に手伝ってくれる」ことです。
■ Copilotが得意なこと
・会議の自動議事録作成や要約
~ 会議中のTeamsで、会話内容を自動でまとめてくれる。終わったあとに「要点だけ」読み返せる。
・メールや資料作成の“たたき台”を用意
~ 過去のメールや資料からAIが自動で下書きを作ってくれるので、ゼロから書き始める必要がない。
・データ集計やグラフ化も一発で
~ Excelの売上データから「今月の売上推移グラフを作って」と頼めば、すぐにグラフが出てくる。
・過去の社内情報やチャットも横断検索できる
~ 必要な情報を「あの資料どこだっけ?」と探し回る手間が減る。
■ ここは注意!Copilotの苦手なこと
・会社独自の業務知識や専門用語には最初は弱い
~ 「会社特有のルール」「業界独自の言い回し」は教え込む(使い込む)ことで精度アップ。
・情報の“正確さ”チェックは必要
AIは間違った提案や古い情報を出すこともあるので、「最終確認」は必ず人間が行う。
・創造的すぎる“独自アイデア”は苦手
~ 新規事業の発案や、クリエイティブな提案はまだ人間の強み。AIは“補助役”と考えよう。
5. 企業でCopilotを使うべき理由――「コスト」「生産性」「安心感」
■ 「AI導入コスト=大きな投資」ではない時代に
「AI=高額で大企業しか使えないもの」と思われがちですが、CopilotはMicrosoft 365を使っている企業なら“追加契約”だけで導入できるため、数十人規模の会社でも現実的に利用できます。
■ 生産性向上は“全員の時短”で生まれる
メールや会議のまとめ作業、社内資料作りなど、誰もが「本当は手を抜きたい」業務をAIに任せることで、1日数十分〜数時間の“隠れた時短”が実現。これが全社員の合計になると、1か月で膨大な生産性アップにつながります。
■ 企業向けCopilotの「安心感」
個人のAI利用と異なり、「誰が・どの情報にアクセスできるか」や「データの保存先」など、ガバナンスやセキュリティを最初から設計できる点が大きな違いです。「情報漏洩の心配を最小限に、安心してAI活用を進めたい」企業こそ、Copilotが選ばれる理由となっています。
Copilotの使い方のコツ――「お使いメモ」をAIに渡すイメージで
Copilotをうまく使いこなすコツは、「自分の“お使いメモ”を作る感覚で指示を出すこと」。たとえば…
×「議事録を作って」
→○「4月10日10時の営業会議の要点を3つにまとめて」
×「資料を作って」
→○「4月の売上推移をExcelのグラフで出して、前年同月比もコメントして」
こうした“具体的な頼み方”を意識するだけで、AIのアウトプットの質がグッと上がります。
また、「AIの回答がイマイチ」と感じたら、「この部分は要らない」「ここは詳しく」など追加で頼むことで、より自分の意図に近づけてくれるのもCopilotの魅力です。

まとめ:「“AI時代の副操縦士”と、まずは小さな一歩から」
AIがいよいよ「現場の働き方を変える時代」になりつつあります。ただ、最初から大きな変化を求める必要はありません。
まずは会議のまとめ、メールの要約、資料の下書きなど、自分が「面倒だな」と思う仕事を1つ、Copilotに頼んでみることから始めてみてください。「自分でやるより早いかも」「これなら安心して使えるかも」――そんな実感を一歩ずつ積み重ねていくうちに、会社全体での業務効率化や生産性向上が見えてくるはずです。
これらのサポートをご希望の方はこちらからご連絡ください!