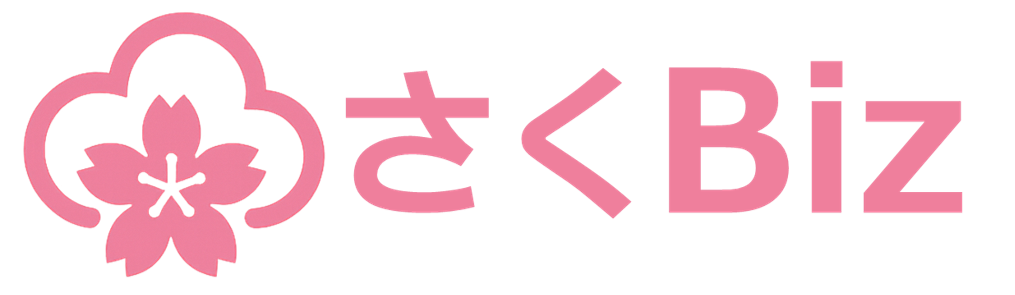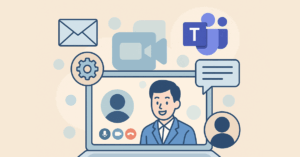システム障害時の「慌てない」対応マニュアル作成法
「突然、メールが使えなくなった」「受発注システムが止まり、業務が進まない」――そんな経験はありませんか?
多くの中小企業にとって、システム障害は決して他人事ではありません。
最近はクラウドサービスや業務アプリケーションの利用が当たり前となり、トラブル発生時の影響は以前にも増して大きくなっています。しかし実際には「誰に連絡すればよいのか分からない」「手順が分からず慌ててしまう」といった声も多く、初動対応の遅れやミスが被害の拡大を招いてしまうケースも少なくありません。
そのためには、障害時の「慌てない」ための事前準備と、現場ですぐ活用できるマニュアルの整備が重要です。
本記事では、特に影響度が高い2つの障害パターン――「クラウドサービス(メールやファイル共有)の障害」と「業務アプリケーションの障害」――に注目し、実践的な対応方法をご紹介します。
よくある障害パターンと影響度
1. クラウドサービス(メール・ファイル共有)障害(影響度:中)
たとえば、ある朝突然「メールが送受信できない」「ファイル共有サービスにアクセスできない」といった障害が発生したとします。
この場合、取引先とのやり取りや資料の共有がストップしてしまい、業務全体の流れに影響が出ます。ただし、すぐに代替手段(電話やFAX、ローカル保存ファイルの活用など)を使えば一部の業務は継続できることが多いため、影響度は“中”程度と言えます。
一方、慌てて対応しようとすると「原因が分からないまま何度も再起動する」「状況報告を怠る」「誰が対応するか不明確」などの混乱が起こりやすく、結果として復旧が遅れるリスクも。
2. 業務アプリケーションの障害(影響度:高)
日々利用する受発注管理システムや顧客管理システムが突然使えなくなると、受注・納品処理や顧客対応が全面的にストップしてしまうことも。このような“影響度が高い”障害時は、短時間での状況把握と適切なエスカレーション(担当部門・外部ベンダーなどへの連絡)が不可欠です。
しかし、現場では「誰がどの手順で対応すべきか不明」「担当者間の連絡が遅れる」「慌てて不用意な操作をしてしまい事態が悪化」といった課題が多く見受けられます。
障害対応マニュアル作成の実践ポイント
システム障害が発生した際に「慌てない」ためには、現場で使える実践的なマニュアルを用意しておくことが効果的です。
ここでは、2つの障害パターン別にマニュアル作成のポイントをご紹介します。
クラウドサービス障害マニュアルの作り方
代替手段の明記
メール障害時には電話やFAXによる連絡、ファイル共有障害時はUSBメモリやローカル保存データの活用方法など、すぐ実行できる代替案を具体的に記載しましょう。
一次対応手順
サービス提供元の障害情報を確認し、同時に自社のインターネット接続状態もチェックする。
「障害発生時に確認するチェックリスト」を用意しておくと便利です。
社内連絡の流れ
どの段階で、誰に、どのように報告するかを決めておきましょう。
たとえば、「まずはIT担当リーダーにチャットで報告」→「必要に応じて全社に周知」など。
業務アプリケーション障害マニュアルの作り方
障害内容の整理と初動対応
「画面が真っ白」「エラー表示が出る」など、発生状況や症状を具体的に記録する項目を設けましょう。
マニュアル内に記入例を盛り込むと、現場でも迷わず使えます。
エスカレーションルートの明確化
自力での復旧が難しい場合は、すぐにシステム管理者や外部ベンダーに連絡できるよう「問い合わせ先リスト」を添付しましょう。
業務継続策の明記
一時的に紙ベースで記録を残す、顧客対応の一次窓口を決めるなど、“障害時の暫定運用”もマニュアルに盛り込むことが重要です。
共通の工夫
・責任者・担当者・連絡経路を明文化
・マニュアルを現場に浸透させるため、定期的な見直しや簡単な読み合わせ会を実施
・実際の障害を想定した「具体的な記入例」「チェックリスト」「連絡フォーマット」などを添付
障害訓練(模擬訓練)の重要性と実施法
せっかくマニュアルを整備しても、現場で使いこなせなければ意味がありません。年に1回、もしくは半年に1回などの頻度で「障害対応訓練(模擬訓練)」を実施し、実際の流れを体験することをおすすめします。
クラウドサービス障害の訓練シナリオ例
シナリオ:「朝9時にメール送受信ができない」という状況を設定
チェックポイント:誰が最初に気づくか、どの順序で情報が社内に伝わるか、代替手段はすぐに用意できるか
業務アプリケーション障害の訓練シナリオ例
シナリオ:「受発注管理システムが突然動かなくなった」
チェックポイント:障害内容の整理・記録、管理者やベンダーへの連絡速度、暫定対応の可否
訓練の工夫
・小規模チームでも実施できるよう、負担の少ない短時間シナリオを作成
・訓練後は振り返りミーティングを行い、「実際に困った点」「改善点」をまとめて次回に活かす
報告・連絡ツールの効果的活用と注意点
障害時は、速やかで的確な情報共有が復旧スピードを左右します。
「誰が」「どのツールで」「どんな情報を」伝えるかを決めておくことが重要です。
チャットツールやグループウェア
即時性があり、関係者全員に同時に伝達できる点がメリット。
ただし、重要な内容はチャット後にメールなどで再通知するなど“二重確認”もおすすめです。
電話連絡
業務アプリ障害など“影響度が高い”場合は、直接連絡で迅速に伝える。
伝えるべき情報の整理(テンプレート例)
・障害発生日時
・障害内容(例:◯◯システムのログイン不可)
・影響範囲(どの業務・部門に影響するか)
・現在の対応状況
など、要点をまとめたフォーマットを用意しておくと、混乱時にも伝達漏れを防げます。

まとめ
システム障害時に「慌てない」ためには、
1)よくある障害パターンごとに実践的なマニュアルを整備すること
2)マニュアルを定期的に見直し、訓練を通じて現場に浸透させること
3)報告・連絡の手順とツール、伝えるべき内容を具体的に決めておくこと
――が不可欠です。
まずは、自社で「起こりうる障害の洗い出し」から始め、簡単な対応マニュアルを作ってみましょう。
できれば年に1回の障害対応訓練もセットで実施すると、いざという時に“慌てない”現場力が備わります。
“慌てず対応できる”組織づくりは、今日からでも着手可能です。
この記事が、その第一歩になれば幸いです。
これらのサポートをご希望の方はこちらからご連絡ください!